かぜには様々な症状や原因があります。
身近な病気だからこそ、よく理解しておけば、
いざというときの対処に役立つはずです。
知っているようで知らない、“かぜ”を学びましょう。

もし、かぜをひいてしまったと感じたら、どのように対処すればよいのでしょうか。ここでは、大切な4つのポイントをお伝えします。
東洋・西洋医学ともに、かぜの治療において重要視されているのが、安静にしてしっかり眠ることです。疲れた体を回復するとともに、体力を消耗しないためにも、できるだけ体を休ませましょう。
もし、せきや鼻水などの症状でなかなか眠れない場合は早めに、いわゆる「かぜ薬」を服用し、症状をやわらげるのも一つの方法です。
かぜをひいたときに体を温める効果がある食材を意識的に摂り、バランスのとれた食事を心掛けましょう。体力の回復や免疫機能の低下を防ぐ効果などが期待できます。
また、水分補給は重要です。水分が不足すると、脱水症状が生じ、症状が悪化するリスクが高まります。1日に合計1.5~2Lほどを目安に、1~2時間おきにコップ1杯程度を常温で摂るといいでしょう。脱水症状を防ぐとともに、症状の悪化を抑える効果が期待できます。
市販のかぜ薬は、病原体を排除してくれるわけではなく、現れている症状をやわらげるための「対症療法」の薬です。体調をよく観察しながら、症状や飲みやすさで自分に合うものを選ぶとよいでしょう。薬局・薬店では薬剤師に相談するとよいでしょう。
鼻水や鼻づまり、くしゃみが主な症状であれば、炎症を引き起こすヒスタミンの働きを抑える抗ヒスタミン成分が含まれている薬が効果的です。また、のどの痛みにはトラネキサム酸やアズレンスルホン酸ナトリウム、セチルピリジニウム塩化物水和物、あるいは漢方エキスを配合したトローチやのどスプレーなどが有効です。なお小児では、抗ヒスタミン薬が有効ではない場合や、好ましくない症状が現れる場合もあるため、これらの購入時には薬剤師に相談するとよいでしょう。
かぜの症状がひどかったり長引いたりする場合は、細菌による二次感染やアレルギー疾患を発症している、あるいはかぜではない他の疾患にかかっている場合もあるので、自己判断せずに、早めに医療機関を受診することをお勧めします。
妊娠中にかぜをひいた場合は、市販薬に含まれる成分のなかには妊婦にとって注意が必要なものもあるため、自己判断で薬を飲むことは避け、必ず医師・薬剤師に相談し指示にしたがって服用しましょう。
 かぜをひいたときはお風呂に入っていいの?
かぜをひいたときはお風呂に入っていいの?
 軽いかぜなら、お風呂で汗を流してすっきりすると、よく眠れるようになり回復を助けることもあります。ただし、熱すぎるお湯に入ると体力を消耗してしまい、かえって逆効果になることもあるので注意が必要です。体調に合わせて、「気持ちいい」と感じる温度や入り方を心がけましょう。
軽いかぜなら、お風呂で汗を流してすっきりすると、よく眠れるようになり回復を助けることもあります。ただし、熱すぎるお湯に入ると体力を消耗してしまい、かえって逆効果になることもあるので注意が必要です。体調に合わせて、「気持ちいい」と感じる温度や入り方を心がけましょう。

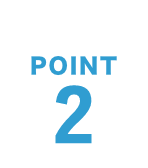 服をたくさん着て汗をかくべき?
服をたくさん着て汗をかくべき?
 熱が上がって寒気がするときは体を温め、反対に熱が出て体が熱く感じるときは薄着にして熱を逃がすようにしましょう。まだ言葉で伝えられない赤ちゃんや、自分で調整ができない高齢の方などは、汗のかき方やおしっこの量を目安にして、着るものや布団をこまめに調整してあげることが大切です。また、汗をかいたままにしておくと体が冷えて体力を消耗するため、こまめに汗を拭いて着替えるようにしましょう。
熱が上がって寒気がするときは体を温め、反対に熱が出て体が熱く感じるときは薄着にして熱を逃がすようにしましょう。まだ言葉で伝えられない赤ちゃんや、自分で調整ができない高齢の方などは、汗のかき方やおしっこの量を目安にして、着るものや布団をこまめに調整してあげることが大切です。また、汗をかいたままにしておくと体が冷えて体力を消耗するため、こまめに汗を拭いて着替えるようにしましょう。

 水分補給はなにがいいの?
水分補給はなにがいいの?
 食事が摂れるときは、水や薄いお茶、薄いジュースなどでも水分補給として問題ありません。しかし、食事を摂れない場合や胃腸炎のときは、体内の電解質が不足しやすいため、経口補水液を使うと効果的です。かぜや胃腸炎のときは、栄養補給と水分補給を意識して行ないましょう。いわゆるスポーツ飲料は、飲み過ぎると糖分が過剰になったり、脱水となった時の水分・電解質類の補正には不適当となります。
食事が摂れるときは、水や薄いお茶、薄いジュースなどでも水分補給として問題ありません。しかし、食事を摂れない場合や胃腸炎のときは、体内の電解質が不足しやすいため、経口補水液を使うと効果的です。かぜや胃腸炎のときは、栄養補給と水分補給を意識して行ないましょう。いわゆるスポーツ飲料は、飲み過ぎると糖分が過剰になったり、脱水となった時の水分・電解質類の補正には不適当となります。

 かぜ薬はどうやって選ぶべき?
かぜ薬はどうやって選ぶべき?
かぜ薬(総合感冒薬)は、様々な症状に対応できるように作られており、主に解熱鎮痛作用のあるイブプロフェン製剤と、アセトアミノフェン製剤の2種類があります。購入の時には、薬剤師や登録販売者に相談して、自分に合った薬を選ぶことが大切です。
また、子どもに解熱鎮痛薬を使う場合は、アセトアミノフェン製剤が好ましい(安全性が高い)とされています。
| イブプロフェン | アセトアミノフェン | |
|---|---|---|
| 特徴 | 解熱、鎮痛効果が高い | 解熱、鎮痛効果は 弱いが、 小児における安全性が高い |
| 服用 年齢 |
15歳以上 | 2歳以上 |
※3ヵ月以上の子どもから服用できるものもありますが、2歳未満の乳幼児は医師の診察を優先してください。
 病院でかぜ薬と一緒に胃腸薬が処方されることが多いのはなぜ?
病院でかぜ薬と一緒に胃腸薬が処方されることが多いのはなぜ?
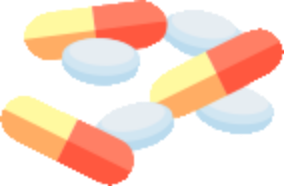 抗生物質(抗菌薬)を飲むと胃腸の調子をくずすことがあり、このような胃腸障害を防ぐために胃腸薬が一緒に処方されることが多くあります。市販薬を選ぶときに「胃への負担が心配」という場合は、薬剤師や登録販売者に相談しましょう。
抗生物質(抗菌薬)を飲むと胃腸の調子をくずすことがあり、このような胃腸障害を防ぐために胃腸薬が一緒に処方されることが多くあります。市販薬を選ぶときに「胃への負担が心配」という場合は、薬剤師や登録販売者に相談しましょう。
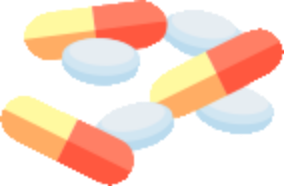
かぜをひいたときに、以前に処方されて家に残っている抗生物質(抗菌薬)を自己判断で飲むのは絶対にやめてください。抗生物質は細菌による感染に使う薬であり、多くのかぜの原因となるウイルス感染症には効かないばかりか、症状を悪化させることもあります。
また、大人用の解熱薬やかぜ薬を子どもに飲ませるのも危険ですのでやめましょう。症状が悪化したり、副作用が出たりするおそれがあります。特にインフルエンザでは急性脳症やライ症候群などの重症合併症を悪化させることもあるため注意が必要です。
薬の使用に不安がある場合は、自己判断せず、薬剤師に相談したり、医療機関を受診したりしましょう。